経営の原理原則
決算書・財務分析
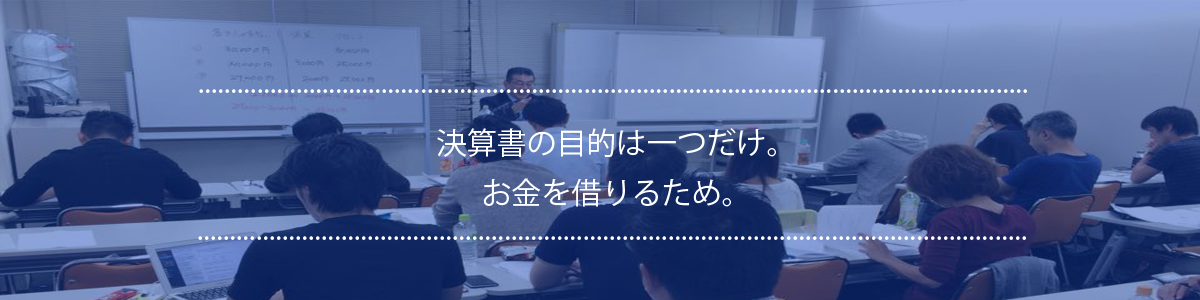
決算書の本当の役割とは?
書店に行くと、「儲けるための決算書の読み方」といったノウハウ本が、所狭しと並んでいます。
数字が苦手な経営者は、それを読むと本当に儲かるのかと錯覚し、そうした本を読みあさります。
しかし、そこには、あなたの望む答えはありません。
もし本当に、決算書が読めたくらいで儲かるのなら、
「銀行員や税理士が商売をすると、大儲けできる」ということです。
そんなこと、あるハズがありません。
決算書の数字は全部ウソ!?
あなたは、決算書の利益は水増しされたものだということを知っていますか?
あんなものを信じて経営していたのでは、いつかは資金繰りに窮することになります。
決算書というものは、税法上のルールにのっとって作成されます。
税務署は少しでも多くの税金を徴収したいわけですから、
会社の実態とはかけ離れて、利益が出やすいようなルールを設定しています。
つまり、決算書の「利益」は、単に税金を支払うための「数字」に過ぎないのです。
そんな作られた「利益」を基に、どんな経営分析をしたとしても、
本当の会社の実態など、見えてくるはずがありません。
経営者が知りたいのは、自分の会社の、本当の実態です。
決算書で「儲かっている」と思っていたら、
「実は、もう手が付けられないくらい、ボロボロの状態だった」ということは、
よくあることです。
決算書が読めたくらいでは儲からない
ここで述べることは、あなたにとって、見たくない現実かもしれません。
しかし、お金の世界は、ギリギリの所まで来てしまうと、残念ながら、何も打つ手がなくなってしまうものなのです。
「気づいた時には、もう遅い」というのが現実です。
ですから、決算書の本当の利益を知ることは、経営者にとって、欠くべからざる仕事といえます。
しかし、一方、現実をそのまま決算書に反映したのでは、銀行から融資が受けられないというのも、事実です。
融資を受けるためには、それなりの決算書が必要になります。
つまり、決算書の最大の目的は、「銀行からお金を借りる」ということなのです。
会社の実態は、実態で把握して、数字からマイナスの兆候が見えれば、すぐに対策を打つ。
その上で、決算書自体は、銀行の融資を受けやすいものにする。
この作業ができるかどうかが、
あなたの会社の命運を分けることになります。
決算書を知ることが倒産回避の第一歩
ここでは、まず決算書の基本ルールを説明し、
それから一歩進んで、決算書に潜む重大なワナを解説します。
また会員用ページでは、
「銀行が、決算書のどの部分の数字を、どのように分析して融資を決定するのか」を、詳しく説明します。
そのためには、まず、決算書の読み方を知らなくてはなりません。
「決算書が読める」ということは、「利益を上げる」という「攻撃」ではなく、
「倒産させない」という、「防御」なのだということを知ってください。
決算書を知ることが、あなたの会社を倒産から救うのです!!
決算書が分かれば、次は財務分析
決算書に潜むワナを理解し、会社の真の実態が把握できたら、次は財務分析です。
あなたの会社の本当の決算書を基に、分析をかけます。
ここで問題になるのが、「分析指標」です。
本で紹介されている指標はあまりに多いため、
どれが重要な指標で、その指標を実際に、どう役立てれば良いのかが分かりません。
それと同時に、分析指標には、「使える指標」と「使えない指標」があるということを知って下さい。
本では当たり前のように紹介されている指標も、実は、普遍性がないということも意外に多いのです。
会社の業態・業種によっては、まったく妥当性がないという分析指標もあります。
これは、私のこれまでの企業再生業務を通して気づかされた、一つの事実です。
会員用ページでは、「実践で役立つ分析指標」と、その使い方について、詳しく解説します。
本来、財務分析という分野は、経営者のためにあるべきものです。
使える指標を選び、それを集中して分析することにより、経営を改善することが第一の目的です。
「分析指標や比率を盲目的に信じる」ことは、
かえって「倒産を早める」こともあるのです!!
決算書が分かれば、すべてが変わる!!
●なぜ決算書の知識が必要なのか?
あなたは、決算書を読むことができますか?
下記に「イトーヨーカドー」「イオン」「ダイエー」という、3つの会社の損益計算書と貸借対照表を掲げてみました。
いかがでしょう?
「どの会社の、どこに問題があるのか」それをすぐに解説できますか?
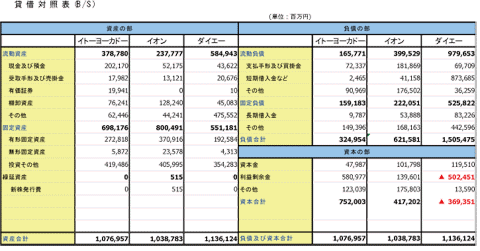
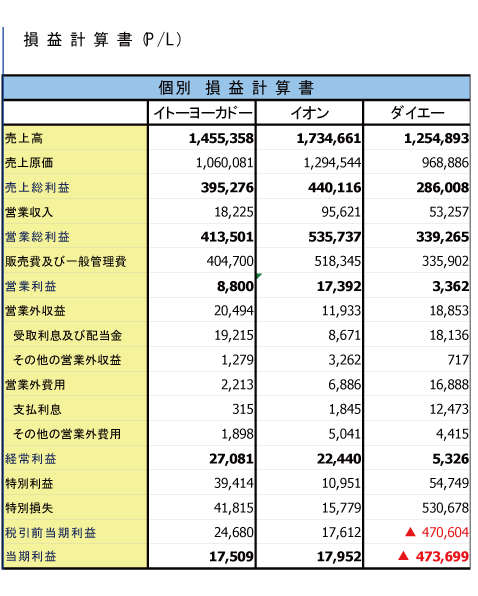
皆さんの中には、「損益計算書、貸借対照表を見るのは初めてだ」という方もいらっしゃるのではないでしょうか?
会計をとっつきにくいものだと考えている方は、少なくないはずです。
損益計算書と貸借対照表は、決算書を代表するモノといわれていますが、
素人目には、なかなか判読することができないものです。
よくわからない数字がいっぱい並んでいる決算書。
ましてやその数値を分析するとなると、
決算書作成のプロである税理士にまかせるしかないと、勘違いをされている方も多く見受けられます。
たしかに「決算書を作る」となると、税理士のような専門的知識がないと難しいと思います。
しかし、「決算書の見方」はそんなに難しいものではありません。
一定のルールさえ覚えてしまえば、
推理小説の謎解きのように、決算書を分析するのが楽しくなります。
それと同時に、知っておいてもらいたいのは、「決算書の利益は、本当の利益ではない」ということです。
税務署が、少しでも多くの税金を徴収するために仕組んだ、「水増しされた利益」なのです。
ですから、決算書の数字をうのみにしてはいけません。
経営者であるなら、自分の会社の実態を知るべきです。
そこから、すべてがスタートします。
税理士は、税務のルールに基づいて、決算書(税務署用決算書)を作成しており、
経営の実態を表す決算書を作ろうとはしていません。
あなたは、アメリカでは、「本当の決算書」と「税務署用の決算書」の2種類の決算書が作られているという事実を知っていますか?
このセクションでは、「税務署用決算書がいかに経営の実態を表していないか」ということ、
「経営に役立つ実態の決算書と、税務署用の決算書はどこが違うのか」を理解していただきたいと思います。
経営者にとって大切なことは、税務署用決算書を、いかに「実態を表す決算書」に読み替え、
自分の会社の実態を把握し、何が何でも「倒産させない」という、防御法を知ることです。
その方法を知っているかどうかが、あなたの会社の命運を分けるのです!
● 決算書を読むことのメリット
「決算書」と一口で言っても、いまいちピンとこない方も多いのではないでしょうか?
何だかよく分からないが、1年に1度、経理担当者や会計事務所が作成する書類といったイメージではないでしょうか。
決算書といっても、様々な種類がありますが、一般的には「貸借対照表」「損益計算書」のことを指します。
つまり、これらが読めるようになれば十分なのです!
では、決算書を読むことができると、どのようなメリットがあるのでしょうか?
1. 自分が所属している会社の状態がよくわかる
会社は、利益をあげることを最大の目標として、動いていくものです。
決算書を読むことによって、「自分の会社が、今現在どのような状態にあるのか」
そして、「この先、どのような方向に向かって進んでいくのか」が分かるようになります。
2. 仕事の成果が会社にどれだけ貢献しているかがよくわかる
「自分の仕事の成果が、会社の売上高、利益にどのように貢献しているのか。それとも貢献できていないのか」がよく分かります。
損益計算書や貸借対照表に記載されている数字は、仕事の成果であり、結果なのです。
3. 会社の長所・短所が把握できるようになる
会社の長所・短所が把握できるようになると、
「もっと利益を出すためには何をすればよいか」そして、「何をしてはいけないのか」の判断が可能となります。

決算の最大の目的は、「その年度にいくら儲かったのか」「会社の経営状態がどうなっているか」を把握することにあります。
そして、その分析結果を元に、「対応策を考える」ことにあります。
本当の意味で、「決算書が読める」ということは、
「決算書のしくみを知る」と同時に、「どのような目的で作成されるのか」、
「税務署用決算書と、実態の決算書が、いかにかけ離れているか」を理解することです。
まずここでは、「貸借対照表」と「損益計算書」の、基本的な仕組みを解説します。
経営分析の基礎になる部分ですので、面倒くさがらずに、頭に入れて頂きたいと思います。
「決算書の読み方」は、一度理解してしまえば、これほど面白いモノはありません。
あなたの会社の実態が、数字でハッキリと表されますので、これほど明確な反省材料はありません。
その分析をもとに、打開策や目標数値を設定し、
一日でも早く行動することが、会社を倒産の危機から救うことになるのです。
決算書その1 貸借対照表(B/S)
■ 貸借対照表のしくみ
「貸借対照表」。。。
やはり難しい言葉です。
英語では、貸借対照表のことをバランスシート(balance sheet 略してB/S)を言いますが、これは「貸借(=左右)が一致している表」という意味となります。
決算書を見てもらえば分かると思いますが、
どんな書式であっても、必ず貸借対照表が一番先にきています。
それは、「貸借対照表が、決算書の中で一番大切」だということを意味しています。
「資産」と「負債」が増えたのか減ったのか、そのバランスはどうなっているのかを読み取り、
最もバランスがとれている状態を目指して、経営を改善していきます。
「会社が儲かっているか、損しているのか」は、
損益計算書に表示される、お金の出し入れだけでは判断できないのです。
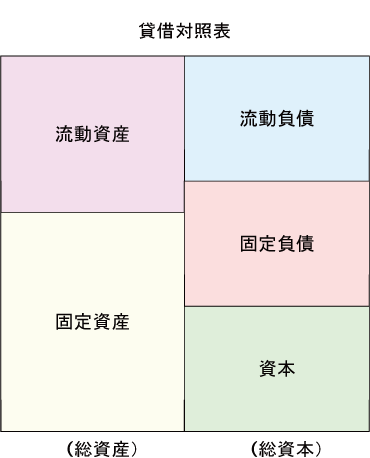
貸借対照表とは、決算日時点での、会社の「財産」と「借金」が一目でわかる表です。
貸借対照表には、やけに堅苦しい言葉が使われているので、難しく思えますが、
大きなくくりで表せば、上の表のようになります。
大きな特徴として、「左右に分かれている」ことが挙げられます。
右側を「総資本」、左側を「総資産」といい、左右の数字は同数になります。
右側の「負債」「資本」は、会社が事業に使う資金を「どうやって集めたのか」を表しています。
調達方法は大きく分けて、以下の3つです。
・人から借りる。(負債の部) → 返済する必要がある。
・株を発行して集める、いわゆる出資。(資本の部) → 返済の義務なし。
・今までの事業を通じて儲けた利益(資本の部)
銀行や人から借りたものは、いずれ返さなければいけないので、「負債」と表されます。
一方、株を発行して集めた資金や、事業を通じて儲かった利益は、
返す必要がありませんから、「資本」とされます。
左側の「資産」は、右側で集めた資金が「何に形を変えたのか」を表しています。
事業を行う上では、現金だけでなく、商品在庫や設備など様々なものが必要になります。
また、取引をしていく中で「後払いで売ったり(売掛金)」「手形をもらったり(受取手形)」することがあります。
これらの「後でお金を受け取る権利」を「債権」といいます。
形態はさまざまですが、現金や預金以外に、「会社がお金を払って取得したもの」が含まれます。
これらは会社の資産ですから、左側に「資産」と表記されます。
「資本の調達」と「運用」は表裏一体の関係であり、両者の合計金額は、必ず一致します。
なぜなら、会社が左側の「資産」を持つために、どのようにしてお金を集めたかを示すのが、右側の「負債」と「資本」だからです。
つまり、右側の「負債」と「資本」で集めたお金が、左側の「資産」に形を変えたということです。
この考え方は、非常に重要なポイントですので、よく覚えておいて下さい。
会員用ページも含め、今後説明する経営分析の基礎となる考え方です。
ここで、資産・負債・資本の3者の関係をご理解いただきたいと思います。
基本的には、家庭の会計、つまり、家計における「財産」と「自己資金」及び「ローン」の関係と同じです。
ある家庭で、現金100万円、3,000万円のマンションを保有しているケース。
これらは、家計にとっては「財産」であり、貸借対照表では左側に表記されます。(下記参照)
そして、これらを、ローンを抱えない状態で保有しているのであれば、
貸借対照表の右側は、すべて自己資金(資本金)となります。

しかし、マンションを購入するためのローンが1,000万円残っていた場合、
その部分は「自分のもの」ではなく、「他人から預かっているもの」(長期借入金)と把握されます。
この場合、貸借対照表の右側は、下記のように表記されます。
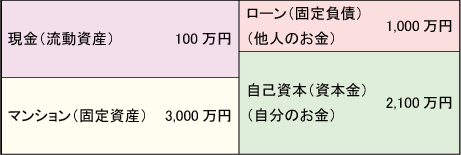
それでは、ここで、より詳しい貸借対照表の例を挙げますので、具体的に見てみましょう。
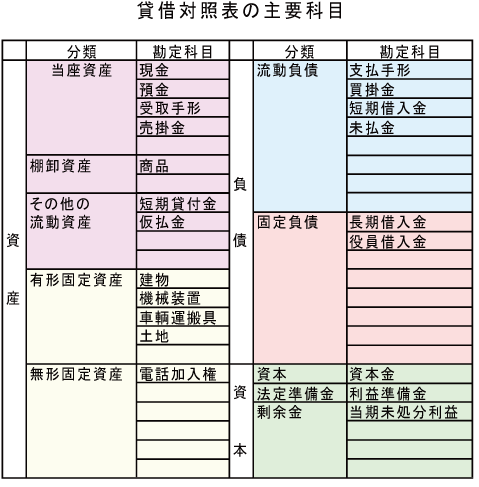
普段あまり見慣れない単語ではありますが、何となくイメージできるのではないでしょうか。
貸借対照表の左側は、「事業のために集めたお金が形を変えたもの」で、
右側は、「そのお金をどうやって集めたか」を表しています。
右側の「資本の部」は、少し分かりにくいと思いますので、簡単に説明します。
「資本金」とは、会社を始める時、または増資した時に集めたお金の合計です。
「法定準備金」は、毎年の決算の時に出た利益の一部を積み立てたものです。
そして、「当期未処分利益」は、過去の利益の積み重なった合計です。
赤字の会社の場合は、この部分がマイナスの表示になります。
■ 流動資産、固定資産とは
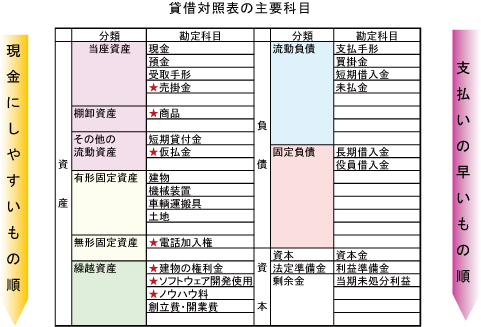
上記に掲げる表は、もう一つの決められたルールにしたがって作成されています。
左側の「資産の部」を、「流動資産」「固定資産」「繰延資産」の3つに、
右側の「負債の部」を、「流動負債」「固定負債」の2つに分けています。
ここでは、「流動○○」と「固定○○」の違いをご理解いただきます。
「流動資産」とは、「決算日から1年以内に現金化されるもの」を示します。 「固定資産」とは、流動資産より、回収期間が長いもの(1年以上)を示します。 「流動負債」とは,「決算日から1年以内に支払わなければならない負債」を示します。 「固定負債」とは、流動負債より、支払期間の長いもの(1年以上)を示します。
"1年"が境目となって、「流動」と「固定」は区分されることとなりますので、
このルールのことを、「ワンイヤールール」と呼びます。
■ B/Sの落とし穴!
流動資産として記載されている、売掛金や棚卸資産の中には、
「1年以内の現金化がおぼつかないもの」が含まれていることがあります。
具体的には、「回収不能の売掛金」や「不良在庫」です。
実は、売掛金、棚卸資産(在庫)は、ワン・イヤー・ルールの例外として、
よほどのことがない限り、「流動資産」に計上されることになっています。
しかし、これはよくよく考えてみると、「あってないもの」という見方をするのが妥当です。他にも、仮払金、電話加入権などの権利といった、「無形固定資産等」も資産の部に計上されるものですが、
これらも「あってないもの」と見るのが妥当でしょう。
また、権利金やノウハウ料といった、「繰延資産」も同様です。
商法では、こうしたものを資産にあげることは認めていないにもかかわらず、税法上の資産として計上されています。
もちろん、このような資産は、「あってないもの」です。(上記表の★印)
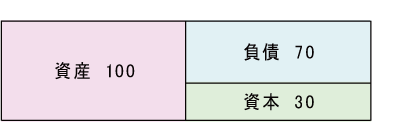
と把握していたものの実態が、不良債権が30や、不良在庫が20あったとすると、実は、
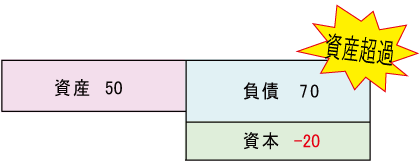
のように、債務超過となっていることもありますので、十分に注意が必要です。
※債務超過とは、資本勘定がマイナスになることです。
つまり、資産の全てが、他人の資本(借入金)によってまかなわれており、
しかも、全資産を売却してもまだ負債が残る財務体質として、非常に危険な状態を指します。
このような状況になったら、まず銀行からの借入は難しくなると理解してください。
■ B/Sによる分析
「企業が倒産しないかどうか」これを判断するための分析方法が"財務安全性分析"です。
そもそも企業の目的は、利益をできるだけ多くあげることにありますが、
これを達成するためには、「将来にわたって企業が倒産しない」ことが前提となります。
その意味で、「安全性」の分析は欠かせません。
では、企業の財務安全性はどのようにチェックすれば良いのでしょうか?
基本的には、「短期」と「長期」の、2つの分析指標があります。
短期的な安全性を見るのが、「流動比率」です。
これは、流動資産/流動負債という算式で算定することができます。
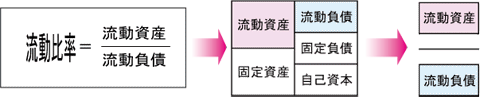
1年以内に支払うべき「流動負債」に対して、その支払手段となる「流動資産」が、どの程度あるのかを見る指標であり、
当然、これが100%以上であることが最低条件になってきます。
逆に100%以下の場合は、1年以内に返済しなければならない負債に、固定資産を充てていることになり、財務的に不安定な状況にあると言えます。
なお、一般的な経営分析の本には、「流動比率は120%以上が望ましい」とされています。
しかし、これは、決算書の数字をそのまま信じた場合であって、実際に流動資産を処分するとなると、等価で売れることはまず考えられません。
ですから、処分価値を帳簿価格の半分とみて、「流動比率は200%以上が望ましい」とするのが実践的です。
このように、流動資産といっても、即時に換金可能なものは限られており、
分子として、「当座資産」(流動資産から棚卸資産以下を除いたもの)という、すぐに換金可能な資産のみで計算するという考え方もあります。
この比率を「当座比率」といいます。
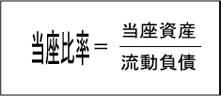
この比率は、「100%以上が望ましい」とされています。
現金化しやすい「当座資産」は、短期の支払いのために直接役立つものですから、
流動負債との関係をみることで、企業の返済能力を、より厳密な形で判断することができます。
例えば、不動産会社のように、非常に金額の大きな土地などの不動産を棚卸資産に計上しているケースでは、
流動資産が膨らみ、「流動比率」だけをみると、実態以上に支払い能力があるようにみえてしまいます。
ところが、「当座比率」をみると低いため、短期的な支払い能力に不安があることが分かります。
このように、流動比率と当座比率を見比べることによって、会社の実態が把握できるというわけです。
「流動比率」や「当座比率」は、銀行が融資を判断する場合にも、必ず使われるくらい重要な数値ですが、
これらの分析数値にも、おのずと限界があります。
いくら流動比率が高くても、「実際の資金繰りではショートすることがある」のです。
たとえば、売掛金の入金は60日後で、買掛金の支払が90日後だとすると、入金の方が早いのですから、支払いに支障はありません。
ところが、売掛金の入金が120日後で、買掛金の支払が60日後ということもあります。
入金の方が遅いケースですが、ほとんどの会社はこうした業態になっています。
これでは、いくら120日後に1000万円入る予定でも、60日後の500万円の支払ができなければ、資金はショートしてしまいます。
流動比率や当座比率では、この点をつかむことができません。
銀行からの資金調達ができないことによる資金繰りの悪化は、財務諸表だけでは把握しきれないのです。
ですから、経営者は、「売掛金の回収」や「棚卸資産の量・販売状況」と、「買掛金の支払いのタイミング」に、
常に目を光らせていなければなりません。
これが、数字の分析とは違った、もうワンランク上の経営者の仕事です。
次に、長期的な安全性を見るのが、「自己資本比率」です。
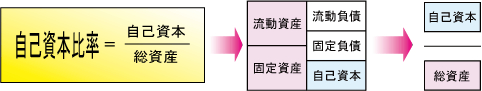
自己資本は、返済の必要ない資金であり、これが相対的に多ければ多いほど、負債返済リスクは減少し、
長期的に見て、財務安全性は増すこととなります。
では、この自己資本比率はどのくらいあれば良いのでしょうか?
負債を自己資本でまかなうという観点から見れば、負債1に対して自己資本1。
つまり、50%が理想値です。
しかし、実際には、35%が当面の目標となります。
業種別にいえば、製造業では20%、卸売業では30%、小売業では45%は必要です。
逆に、20%を切ると、健全とはいえません。
倒産会社のほとんどは、自己資本比率20%以下です。
最低でも、負債の半分は自己資本でまかなう必要がありますので、
やはり30%以上の自己資本比率は、キープしておかなくてはなりません。
自己資本比率をみる場合、注意すべきことがあります。
それは、「この比率が高ければ高いほど良い会社なのか」ということです。
確かに低ければ安全性に問題がありますが、反対に高ければ良いというものでもありません。
中には、この比率が90%以上の会社もあります。
高い比率は、安全性が高いという証拠ですから、それは問題ありません。
しかし、逆に言えば、超安全な会社の本質は、「保守的」だということです。
自己資金だけでは、積極的な経営はできません。
会社というものは、ある程度のリスクを甘んじて受けないと、成長しないものです。技術革新や市場の拡大に乗り遅れ、いずれジリ貧になって、気づいた時には打つ手がなくなってしまいます。
自己資本比率の極端に高い会社は、「成長性に問題がある」ことが多いのです。
決算書その2 損益計算書(P/L)
■ 損益計算書とは
そもそも、会社の利益計算をおこなう、「損益計算書」とはいったい何なのでしょうか?
「損益計算書」は、「企業の一定期間における経営成績」を示す財務諸表で、
「貸借対照表」とともに、財務諸表の中でも主要なものです。
企業の1年間の活動成果は、
損益計算書の中で、「収益」「費用」「利益(または損失)」という形で公表されます。
簡単に言いますと、「会社が1年間でどれだけの利益を稼ぎ出したか」を計算する書類ということです。
なお、一般的には、損益計算書は、profit and loss statement(P/L)と呼ばれます。
つまり、簡単に示すと
![]()
となります。
現金100万円を、すべて自己資金で保有している家計のケースで例えてみます。
これから1年間で、給料500万円を現金でもらい、生活費400万円を現金で支払ったとします。
すると、収入500万円-費用400万円で、差し引き利益は100万円となり、その100万円が自己資金に追加されます。
よって、2年目の貸借対照表は、現金200万円、自己資金200万円がスタートとなります。
このケースでは、現金の増減=損益となっていますが、実務では、必ずしもこのようにはいきません。
なぜなら、経済の拡大発展に伴って現れた、「信用取引」があるからです。
仮に今の例で、400万円の生活費のうち、300万円を現金で支払い、100万円をツケ(信用)で支払ったとします。
100万円については、物は手に入れましたが、一方で、お金の支払いは待ってもらっている状態です。
この場合、コストの認識は、現金を支払った分の300万円だけとするのでしょうか?
答えはNOです!
物の提供を受けた分ということで、信用取引分の100万円を加え、400万円と考えることになります。
すなわち、会計では、売上、コストともに、その計上をする時期を「発生時」でとらえます。
「現金の受け払い」にこだわらずに、
物やサービスの提供をした、あるいは受けた時点で、損益を認識することとなります。
このように、「発生時」に損益を計上する会計を、「発生主義会計」といい、
これが、会計が分かりにくいといわれる原因の一つです。
しかし、これは、その企業の状況をより正確に表すためには、欠かせないルールです。
■ 収益とは
「収益」とは、一言でいうならば、
商品を売上げた代金や、銀行にお金を預けていた場合にもらえる利息などのことです。
ex) 売上、受取利息、受取家賃、有価証券売却益、固定資産売却益、雑収入
■ 費用とは
「費用」とは、いわゆる収益を得るために支出したコストです。
例えば、これから商品を売って一儲けしようと考えたとします。
まず、何が必要でしょうか?
当たり前のことですが、まずなんといっても「商品」が必要です。
この商品を仕入れるために支出した金額を、一般的に、「売上原価」と言います。
売上原価以外にも、商品を売る営業マンなどに支払う給料(人件費)、チラシなどの宣伝に費やした広告宣伝費、
電気代、水道代、ガス代、交通費、家賃、駐車場代、文房具代などの消耗品代・・・
必要な経費は、列挙していくとキリがありません。
■ 損益計算書の様式
損益計算書にも、報告式と勘定式の2つの様式がありますが、一般的には、報告式を用います。
理由は単純ですが、報告式の方が見やすいからです。
報告式は、上から下に損益を計算する形になっており、
計算の過程が段階的に示されていて、非常に見やすい形式となっています。
損益計算書の雛形
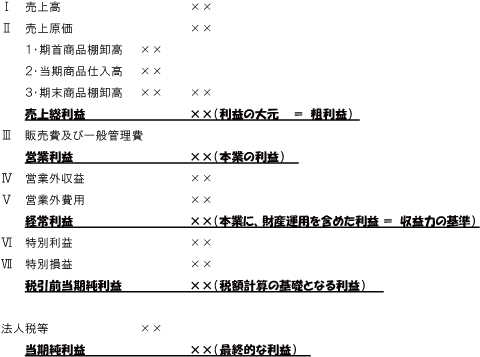
■ P/L計算方法
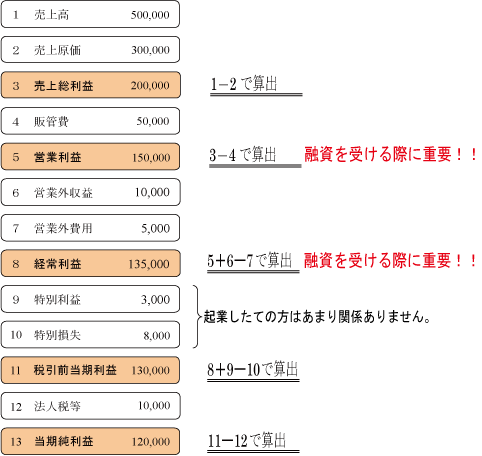
■ 5つの利益とは

![]()
「売上総利益」は、売上行為のみによって得られた利益のことで、一般に「粗利益」といいます。
粗利益は、「人件費」や「家賃」などの経費を引く前の利益であり、これをしっかり稼ぐことが、企業経営の出発点になります。
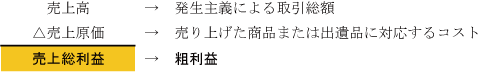
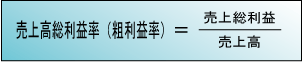
粗利益率は、業種によって異なります。
一般に、流通業、製造業、サービス業の順で、粗利益率は高くなっていきます。
粗利益率が高くなっていくのは、それだけ、取引規模に対する付加価値の金額が、大きいからです。
流通業のように、物を流すだけのビジネスの場合、
創意工夫をこらす場面が少なく、相対的に付加価値率は小さくなります。
それに対して、製造業、サービス業では、
製品やサービスに創意工夫をこらす余地が大きいため、相対的に付加価値率は大きくなるわけです。
ただし、単純に、売上高総利益率が高ければ良いというものではありません。
「従業員一人当たりの付加価値」を見ることが大事です。
詳しい説明は、会員用のページで行うとして、ここでは、基本的な考え方と、その計算方法を解説します。
100円ショップのような「小売業」は、商品を40円で仕入れて、100円で売ります。
このときの儲け60円を、「付加価値」といいます。
決算書上では、「売上総利益」と同額となり、これを「粗利益」ともいいます。
しかし、「製造業」や「建設業」「工務店」の場合は、まず材料を仕入れ、従業員が商品を組み立てます。
従業員だけで間に合わない場合は、仕事を外注に出します。
仮に、販売価格1,000万円の商品が、材料を外注費で700万円、従業員の給料が100万円かかったとすると、
儲けは200万円になります。
この200万円が、「粗利益」になるのですが、「付加価値」は、200万円ではありません。
こうした業種の場合は、商品の組み立てに擁した従業員の給料を、引いて計算しないのです。
つまり、この場合の「付加価値」は、300万円になります。
業種によって、「付加価値」と「粗利益」の数字が変わりますので、注意して下さい。
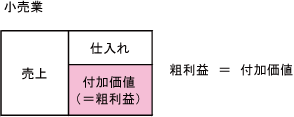
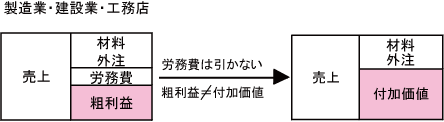
こうして、算出した付加価値を、全従業員数で割って下さい。
これを、「一人当たりの付加価値」といい、会社の経営戦略を考える上での、重要な数値となります。
「この数値を高めるための方策を考えるだけで十分」といえるくらいの、最重要数値です。
これから、その数値の具体的算出方法と、基準値を解説します。
小売業の場合は、単純に、決算書の「売上総利益」を、従業員数で割ってください。もちろん、社長や取締役も従業員数に含めて下さい。
アルバイトやパートは、0.5人で計算します。
製造業や建設業・工務店の場合は、注意が必要です。
「売上総利益」に、商品を組み立てる現場で働く従業員の給料やボーナス、社会保険料などを足した数字を、
全従業員数で割ります。
こうして算出された「一人当たりの付加価値」ですが、
この数字の平均値は、中小企業で1,000万円、上場企業で1,500万円と言われています。
ちなみに、トヨタは2,000万円です。
しかし、この平均値は、非常に業績の良い会社が、数字を押し上げていますので、
実際の中小企業の平均は、700万円くらいです。
仮に、一人当たりの付加価値が、250万円だとすれば、
社長も含めた従業員の給料の平均額が、250万円なら赤字ということです。
それ以上の給料を支払ってはいけないということです。
では、700万円を目標値にすればいいのか?
それは違います。
一人当たりの付加価値が、700~1,000万円程度では、内部留保など出来ません。
運転資金の捻出ができるだけで、
将来のための投資までは手が回らないため、結果として会社は、ジリ貧になってしまいます。
この数値の最低合格ラインは、1,500万円です。
会社を大きくしたいのなら、2,000万円以上を目指さなくてはなりません。
「一人当たりの付加価値」は、会社の管理数値の中でも、3本の指に入る最重要数値です。
この数字を上げることだけ考えていれば、とりあえず会社は安泰です。
しかし、そのためには、会社のお金の流れを完璧に把握する必要があります。
なにやら難しそうに聞こえますが、コツさえつかめば、誰でも簡単に理解することができますので、ご安心下さい。
「お金の流れのつかみ方」と、「一人当たりの付加価値を上げる方法」については、
会員用ページで、具体的に解説します。
話は戻りますが、十分な粗利益が得られない場合は、何らかの対策を講じる必要があります。
たとえば、売上高を増やす、販売価格を上げる、売上原価(仕入や製造コスト)を下げる、といった手法がありますが、
どれか一つに偏ると無理が生じます。
全体のバランスを考慮しながら、自社に最も適した対策を考えるようにしましょう。
なお、粗利益をよく検討した上で、人件費をはじめとする経費節減に努める、借金を減らして支払利息の軽減化を図るなど、
全体的な支出を抑えることも、純利益向上につながります。
そのあたりの具体的な方策についても、会員用ページで、項目ごとに実例を上げながら詳しく解説します。
![]()
「営業利益」とは、「売上総利益」から、「販売費及び一般管理費」を控除して計算される利益であり、
会社の「本業による利益獲得力」を示します。
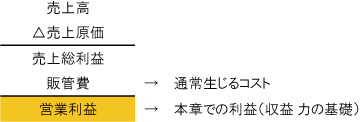
販管費(正確には販売費及び一般管理費)には、広告宣伝費や販売促進費などの販売拡大の為のコストや、
荷造り、発送などの流通コスト、役員報酬、従業員の給料や賞与といった人件費、事務所の家賃、機械の減価償却費などが含まれます。
ただし、製造業の場合、現場の労務費や機械の減価償却費、リース料など工場でかかったコストは、
販管費でなく、いったん製造原価に算入された後、在庫の売却を通じて、「売上原価」に計上されることとなります。
このあたりのことは、先ほど簡単に説明しましたが、
この「原価」という考え方は、経営戦略を立てる上で、とても重要なものです。
経営者であるならば、必ずマスターしなければなりません。
「原価」については、とてもここには書ききれませんので、詳しい説明は、会員用ページに譲ります。
営業利益の数値は、会社の本業が生み出した儲けを表します。
支払利息などの財務費用を差し引きする前の利益ですので、
会社の財務構造の影響を受けることのない利益、すなわち「本業が稼いだ利益」となります。
したがって、「営業利益」は本業の強み、弱みが顕著に表れる重要な利益です。
営業利益が大きいということは、それだけ、収益力があるということです。
しかし、単純に金額が大きければいいかというと、決してそうではありません。
営業利益に限らず、利益を見るときには、その金額だけでなく、売上高に対する割合を見ます。
この割合を、「売上高営業利益率」といいます。
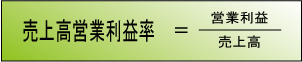
例えば、売上高10億円で、営業利益が5,000万円の会社があるとします。
この会社の売上高営業利益率は、5%です。
一方、売上高は5億円ですが、営業利益が同じく5,000万円の会社があるとします。
この会社の営業利益率は、10%です。
つまり、後者の方が、儲けの効率が良いということです。
先ほど述べた「売上高総利益率」や、「売上高営業利益率」は、数値が高いほど良い指標ということになります。
しかし、売上高総利益率が悪いと、収益性が悪く、その会社はどうしようもないかというと、
一概にそうとも言いきれません。
例えば、卸売業などは、販売量の多さが課題となるため、
売上高総利益率を犠牲にしてでも、売上数量を確保しようとします。
しかし、製造業では、こうした薄利多売では経営困難に陥りますので、売上高総利益率を重視します。
つまり、この数値は、業種や業態の特徴が現れる数字だということです。
「売上総利益率」の一応の目安は、小売業では30%、卸売業では15%、製造業では30%、飲食業では60%ですが、
「同業他社と比べて劣っていないか」をチェックすると同時に、「前年と比べて悪化していないか」を、チェックすることが重要です。
また、「売上高営業利益率」についても、最低でも10%は欲しいところですが、
ここでも、「同業他社との比較、前年比をチェックする」ことが大切です。
![]()
「経常利益」とは、営業利益に、本業以外で生じた収益・費用のうちで、
経常的なもの(特別または臨時でないもの)、つまり「営業外収益」「営業外費用」を、加減したものです。
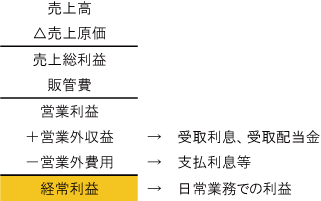
本業が稼いだ利益に、本業以外の「収益」と「費用」を、プラスマイナスしたものが「経常利益」です。
正常な状態で会社が稼いだ1年間の利益、すなわち、「会社の実力を示す利益」となります。
たとえば、借入金が大きい会社では、
営業利益が大きくても、借入金の支払利息などの財務コストが大きく、経常利益がなくなることがあります。
起業間もない会社であれば、営業利益と経常利益は、ほとんど同じ数字になると思います。
逆に、この2つの数字が極端に違うようだと、注意が必要です。
営業利益に対して、経常利益が小さい場合は、「営業外費用が大きくなっている」と考えられます。
起業家の場合、営業外費用の大部分を占めるのは、「支払利息」です。
支払利息が多いということは、借金が多いということですし、手形を割引いて現金化しているということになります。
つまり、資金繰り状況が、悪化しているということです。
一方、営業利益に対して、経常利益が大きい場合は、「営業外収益が大きくなっている」と考えられます。
預貯金の金利としての「受取利息」や、
手持ち有価証券を売って得た「有価証券売却益」が、過大になっているケースがほとんどです。
この場合は、資金繰り面では安定しているようですが、
実は、「手持ちの資金を有効に使わず、そのまま寝かせている」ことが考えられます。
長期的に見た場合、投資効率の悪い会社は、徐々に衰退していく結果になります。
経常利益が多いと安心せず、財務内容のチェックを怠らないで下さい。
経常利益については、2つの重要な指標があります。
まず一つは、「一人当たりの経常利益」です。
例えば、経常利益100万円で従業員10人の会社があるとすると、一人当たりの経常利益が10万円です。
中小企業であれば、こうした会社はたくさんあります。そして、倒産するのも、こうした会社です。
一人当たりの経常利益が、10万円ということは、
社員全員に年間10万円以上の食事をごちそうしたら、赤字ということです。
これでは、月に1万円程度の福利厚生もできません。もちろん、給料のアップもできません。
まず、最低基準を、毎月の借入返済額に設定して下さい。
これをクリアしなければ、話になりません。
その上で、目標値を100万円以上に設定して下さい。できれば、200万円を目指すべきです。
これを達成すれば、資金繰りなど考える必要のない経営が可能になります。
もう一つの指標が、「総資本経常利益率」です。別名ROAともいいます。
この指標も、すべての経営分析数値の中で、トップ3に入るほど重要な数値です。
これは、経営効率を見る上では、かかせない数字です。
つまり、「いくら使って、いくら儲けたか」ということです。
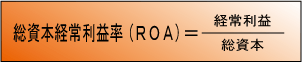
起業家のように、自前の資金や他人からの借金などを元手にビジネスを行う場合、
できるだけ効率よく利益を上げる必要があります。
つまり、いかにして最小限の元手(資金だけでなくヒトや時間も含みます)で、最大限の利益を上げるかが、最重要課題なのです。
中小企業では、この数字が1%以下の会社が、たくさんあります。
もし、あなたの会社がそうなら、会社をたたむことを考えた方が良いかもしれません。
1%以下ということは、経営などしないで、その資金を外貨預金にでも預けている方が、より高い利回りで稼げるということです。
この指標の一般的な基準値は、7%だといわれています。
しかし、これは、大企業向けの数値です。
起業間もない会社が、7%程度の利益しか出せないのでは、話になりません。
なぜなら、利回りというものは、運用資産が少ないほど、高くなるからです。
何百億円も資産を持っている大企業と、数千万円程度の資産しか持っていない起業家では、
利回りが違って当たり前です。
起業5年目までの会社では、総資本経営利益率は、20%は必要です。
特に、総資産が少ない起業初期においては、40~50%を目標にして下さい。
この「総資本経常利益率」は、会社の管理数値として、さまざまな応用が可能です。
そのすべてを紹介していると、いくら紙面があっても足りませんので、その一つを紹介します。(他の応用例は、会員用ページで紹介します)
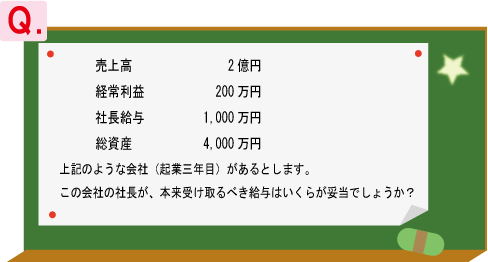
これを、総資産経常利益率(ROA)の適正値から算出します。
起業3年目の、ROAの最低合格ラインは20%でした。そう考えると、この会社の経常利益は
4,000万円×20%=800万円
が妥当だということになります。
実際の経常利益は200万円ですから、その差額600万円(800万円-200万円)は、本来受け取れない給与です。
つまり、この会社の社長の給与は、400万円(1,000万円-600万円)が妥当だということです。
会社を存続させたかったら、給与を400万円に減額するか、
もしくは、経常利益を800万円に上げるべく、経営改善するしかないのです。
これは一例に過ぎませんが、
このようにROAを管理数値として応用することにより、努力目標が明確になります。
このように、管理数値とは、
会社の実態を浮かび上がらせると同時に、経営者のモチベーションアップに繋がるのです。
![]()
「税引前当期純利益」とは、企業の正常な収益力である経常利益に、
臨時的な儲けである「特別利益」、一時的な損失である「特別損失」を加味した損益のことです。
つまり、一会計期間に発生した、すべての収益からすべての費用を差し引いた、企業の処分可能利益です。
簡単に言えば、「税金を支払う前のトータルな利益」となります。
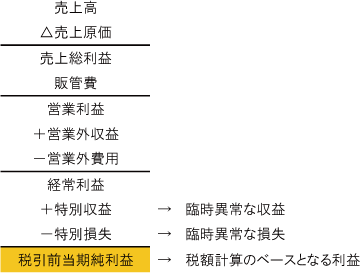
会社を経営していると、風水害にあって損失を出したり、不動産を処分して臨時収入を得たり、といった特殊事情が発生します。
このように、「経常利益」の部と切り離して、「特別損益」の部を設けることで、
会社の「通常の状態の損失」と、「特殊事情を加味した損失」を区別できるわけです。
こうした方が、会社の業績が、より確かにつかめるのです。
![]()
「当期純利益」とは、「税引前の当期利益」から、「法人税」を差し引いた利益であり、
簡単に言えば、「会社に最終的に残った利益」になります。
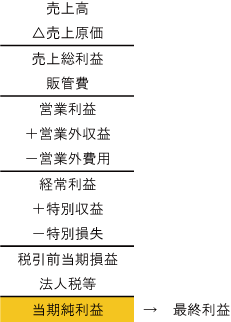
ここで簡単に、法人にかかる税金について、述べてみます。
大きく分けると、次の3つがあります。
・法人税(国税)
・住民税(地方税)
・事業税(地方税)
税金の計算は、損益計算書の「税引前当期純利益」そのものを、基準にするわけではありません。
税法に定められた調整をした上で、課税所得額が決められます。
例えば、「交際費」は、会計上は費用に計上されますが、税法上は、一定額以上は経費とは認められません。
資本金の少ない起業家レベルの会社であれば支出額の20%が、
資本金5,000万円以上の会社であれば、支出金の全額が、税務上の経費(損金)とは認められません。
つまり、大企業は、「交際費」の金額に税金がかかるのです。
税率は、経済環境の変化や租税政策によって、毎年のごとく変化します。
法人税、住民税、事業税を合わせると、利益の40%~50%程度が税金とされます。
なお、赤字法人であっても、住民税の均等割(最小法人で7万円)のみは支払うこととされています。
儲かっているハズなのになぜカネが無いのか?
経営者になれば、「決算書上は利益が出ているのに、思っているよりも現金残高が増えていない」という感覚を持つことがあると思います。
ここでは、なぜそのような状況になるのかを説明してみます。
■ 起こりうる勘違い
商品をお客さんに売れば、その金額が「売上高」になります。
当たり前のことのように思えますが、ここに小さな疑問が生じます。
それは、「どの段階で売上になるのか」という事です。
現金商売である小売業の場合は、
商品の引渡しと現金の受取りが同時に行われますから、この時点が、「売上になる」時です。
しかし、ほとんどの商売は、その場で現金をもらうわけではありませんので、
「どの時点をもって売上とするのか」に疑問が生じます。
1. 商品の注文を受けた時 2. 商品を届けた時 3. 代金の請求をした時 4. 売上代金が入金された時
あなたは、上記のうち、どの時点をもって売上とするのか分かりますか?
答えは、2. の「商品を届けた時」です。
4. の「売上代金が入金された時」ではありません。
2. のように、会計上では、現金の授受とは関係なく、
「発生」の事実に基づいて、売上や費用を計上することになっています。
これを、「発生主義」といいます。
逆に、4. のように、入金・出金という「現金」の増減の段階で、
売上や費用を計上しようという考え方もあります。
これを、「現金主義」といいます。
この2つの考え方の違いが、経営者に「思ったより現金が増えていない」と思わせる原因の1つになっています。
例えば、商品は売れたが、現金をもらうのが1ヶ月後の時、「発生主義」では、商品が売れたときに売上を計上します。
しかし、「現金主義」の場合は、1ヶ月後の現金を受け取ったときに売上を計上します。
ここで、「現金主義」と「発生主義」の間に、売上の計上時期にズレが生じるのです。
また、仕入れのときも同様です。
現金で商品を仕入れた場合、「現金主義」では、支払った時点で仕入として経費を計上します。
しかし、「発生主義」の場合は、その在庫が売れたときに初めて経費として計上されます。
(ちなみに、売れるまでの期間は、「資産」として貸借対照表に計上されています)
当然、資金繰りは「現金主義」で行いますから、
商品を渡した段階で売上計上する、「発生主義」との間にギャップが生じるわけです。
つまり、決算書での利益計算は、「発生主義」で処理されていますが、感覚としては、どうしても「現金主義」になりがちなため、
「儲かっているハズなのに、手元にお金がない」という現象が起こるのです。
最悪の場合、損益計算書上では黒字なのに、キャッシュが足らないために倒産してしまう、「黒字倒産」ということもありえます。
実際に利益のあがっている企業でも、
資金繰りが順調でなければ、企業活動を円滑に行えず、経営的に窮することになります。
反対に、収益性が多少低くても、資金繰りさえ順調であれば、事業を維持できますし、
たとえ赤字でも、資金繰りが続けば、企業は存続できるのです。
これを、損益計算書と実際の現金の動きを比較して、より具体的に説明してみます。
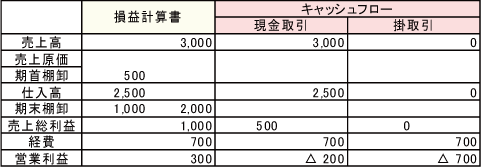
損益計算書では、すべての収益から、すべての費用を差し引き、
プラスであれば利益、マイナスであれば損失、ということになります。
上の例では、売上から売上原価、経費を引いて、300円の利益が出ています。
しかし、実際の現金の動きは、
売上として3,000円が入ってきて、仕入2,500円、経費700円を支払い、差し引きの現金残高は、△200円になっています。
このように、仮に損益計算書では利益が出ている場合でも、同じだけ「現金が増えている」とは限らないのです。
つまり、「利益」と「キャッシュの増加」は、イコールではないのです。
このギャップを埋めるための考え方が、「信用取引」です。
あなたは、クレジットカードを利用して、買い物をしたことがあると思います。
この場合は、商品の受渡しと、現金の授受は同時に行われず、時間的なズレが生じる事になります。
このように、相手を信用することによって成り立つ取引のことを、「信用取引」といいます。
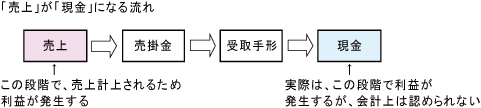
会社の場合、このクレジットカードの役割をするのが、
「売掛金」「買掛金」「受取手形」「支払手形」といった「信用取引」です。
つまり、取引が発生し、その代金が実際に入金・出金されるまでの間は、
「売掛金」「買掛金」「受取手形」「支払手形」という形で、処理されているということなのです。
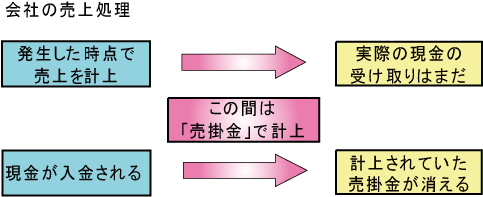
会計上の利益を分かりにくくしている原因の一つは、「現金主義と発生主義の認識の差」です。
しかし、実はもう一つ、経営者に、「思ったより現金が増えていない」と思わせる原因があります。
これこそが、「決算書の利益は信用できない」最大の要因です。
それは、「会計上と税法上とでは、経費の認識に差異がある」という事です。
本来は、経費で落とすべき内容の金額が、税法上の経費にならないのです。
そして、そのやり場に、貸借対照表の「資産の部」が使われている事が問題なのです。
この点については、次の項目で詳しく説明します。
要因その1 減価償却 要因その2 棚卸資産 要因その3 売掛金(貸倒損失・貸倒引当金) 要因その4 納税・資金繰り 要因その5 借入金
決算書の「利益」は、なぜ信用してはいけないのか?
~決算書に潜む破滅のワナ~
● 要因その1 減価償却
■ 減価償却とは
固定資産(例えば建物とか車両、コピーやFAXなどのOA機器etc)を購入しても、会計上は、すぐに経費にはなりません。
会計上の処理は、取得時に、貸借対照表の「資産の部」に、「固定資産」として計上します。
これらの資産は、会社を経営していくうえで、何年にも渡って使用可能なものですので、
その使用可能年数で、徐々に経費にいくことになります。
これを、「減価償却」といいます。
そして、経費にしていく一定期間を「耐用年数」、その年の経費になった額を「減価償却費」といいます。
そして、ここで問題になるのが、「耐用年数」です。
税金を計算する上で、「耐用年数」が会社によって違っていたら不公平にあたるため、
国が定めている年数で、減価償却費を出さなくてはなりません。
「国が定める耐用年数」が、「実態に即した年数」であれば問題ないのですが、
国も税金をできるだけ多く徴収したいため、「実態よりも長い年数」となっています。
これがどういうことを意味するのかは、後で、事例と共に説明します。
■ 減価償却資産の範囲
減価償却を行い、経費化していかなければならない固定資産(減価償却資産)は、下記に掲げるとおりです。
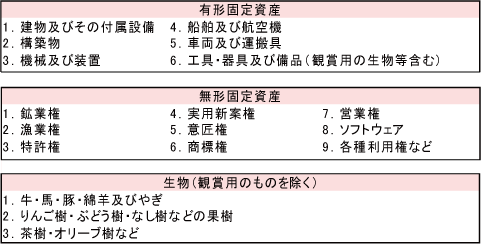
■ 計算方法
1. 定額法
購入金額に90%を掛けた金額に、さらに償却率を掛けて減価償却費を計算する方法で、 計算上の償却費は、毎期定額となります
<計算式>
購入金額×90%×法定耐用年数表で定められた定額法の償却率
上記の算式に基づいて算定した償却限度額が、普通に減価償却をする時の償却額になります。
ex)
建物を2,000万円で、1月1日に購入しました。当期の償却額は?
(耐用年数は20年で、償却率0.050 事業年度は1月から12月と仮定します。)
算式) 20,000,000×0.9×0.050=900,000
この建物の減価償却額は、90万円で、これから毎年90万円ずつ、減価償却費として20年にわたり経費処理します。
2. 定率法
購入金額から今まで経費として計上した減価償却費の合計(減価償却累計額といいます)を引いた残額(未償却残高)に、償却率を掛けた金額を償却額とする方法です。
特徴として、初年度が一番減価償却費が大きくなり、徐々に減価償却費は少なくなります。
<計算式>
(購入金額-減価償却累計額)×法定耐用年数に応ずる定率法の償却率
ex)
大型コンピューターを200万円で1月1日に購入しました。
初年度と2年目の償却額は?
(耐用年数は4年、償却率は0.438 事業年度は1月から12月とします)
初年度)
2,000,000×0.438×=876,000
二年度目)
(2,000,000-876,000)×0.438=492,312
このコンピュータの減価償却額は、初年度87万円、2年目が49万2312円となります。
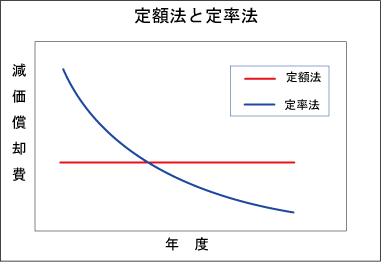
定額法
・事業年度ごとに費用を平均配分する。
・未償却残高の計算が容易。
定率法
・資産が新しい時期に多くの償却費を計上することができる
■ 問題点
例えば、こんな事例を考えてみます。
レストラン業を営もうとする人が、起業準備の一環で、テナントとして借りている店舗の内装を、流行の雰囲気にしようと考え、3,000万円の工事を施工しました。
内装工事は、附属設備に該当しますので、耐用年数20年で減価償却を行います。
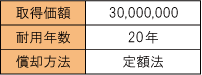
当然ですが、税金を計算する上では、20年かけて費用化していきます。
しかし、これは実情をまったく反映していません。
飲食業を営まれている方は、お分かりだと思いますが、
平均すれば5年ほどで、再度、内装工事が必要になります。
なぜなら、この競争の激しい時代に、同じことを続けて売上が維持できるのは、せいぜい3~4年だからです。
飲食店の場合、よほどの立地条件でない限り、開店後3年ほどたつと、売上が徐々に落ちていきます。
そして、「何らかの手を打たないとダメだ」と切実に感じ始めるのが、5年目くらいです。
つまり、実際には、5年しか資産として存在していなかったのにもかかわらず、
会計上は、20年という長期に渡って、貸借対照表の資産の部に君臨し続けるわけです。
これでは、現実の経営と会計が、大きく乖離してしまいます。
どれだけ実態とかけ離れるかというと・・・
20年で計算した場合
30,000,000×90%÷20=1,350,000
毎年135万円ずつ経費化されます。
しかし、実態に即した5年で計算した場合
30,000,000×90%÷5=5,400,000
つまり、税法と実態の差は、毎年405万円(540万円-135万円)にもなり、税理士が作成した決算書の利益より、会社の本当の利益は、405万円も少ないのです。
仮に、このレストランが、決算書上は毎年100万円の利益を上げていたとしても、実際は、毎年305万円の赤字(100万円-405万円)だということです。
5年後に、内装工事が必要になった時には、決算書上は500万円の内部留保があるはずなのに、
実際は、1,525万円の赤字会社ということです。
これでは、リニューアルどころか、ギブアップするしかありません。
あなたは、「そんなことになるなら、出来るだけ実態に近づけるため、少しでも多くの減価償却をすべきだ」と考えたかもしれません。
しかし、ここにも、税務署が仕組んだワナがあります。
先ほど、減価償却には2通りの方法があり、
「定率法」を使えば、新しい時期に多くの償却費を計上できると述べました。
「それなら、定率法で減価償却すれば良いじゃないか」と思われるかもしれませんが、
実は、それは無理なのです。
なぜなら、建物については、「定額法」しか適用できないと税法で決められているからです。
最も金額の大きな「建物」について、定額法しか税務署が認めないということにも、「少しでも多くの税金を取るために、利益の出やすいルールを決めている」ということがお分かりいただけると思います。
● 要因その2 棚卸資産
■棚卸資産とは
販売を目的として、保有・製造中の財貨又は用役などの棚卸しをすべきもので、下記に掲げる資産が該当します。
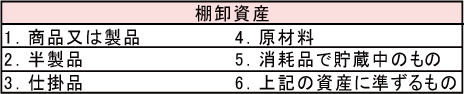
「棚卸資産」とは、いわゆる「在庫」のことで、
実際に商品が売れるまでは、会社の「資産」として、貸借対照表に計上されます。
売れる見込みがあるから、資産計上されている在庫であれば問題ないのですが、
売れる見込みのない在庫まで資産計上されていることがよくあります。
これが、「不良在庫」と呼ばれるものです。
仮に100万円分の不良在庫が、資産に計上されていたなら、それは100万円の「利益」が、実態より多く計上されていることを意味します。
一般的に、棚卸資産は、仕入れた値段そのままで資産計上されていることがほとんどです。
しかし、すでに売れないものを、仕入れた価格でいつまでも資産として計上しておくことは、
経営の実態を表しておらず、経営の判断を誤る原因にもなります。
どんなものでも、購入した瞬間から「減価」が始まります。
新車を買って一度も乗らなかったとしても、購入金額で売買できることなどあり得ません。
商売で仕入れたモノは、消費物ではありませんので、
急激に「減価」が始まるということはありませんが、それでも「在庫リスク」はあります。
いくら商品が売れて利益が出たとしても、
最後に在庫が残れば、そんな利益など、一瞬で消し飛んでしまいます。
ですから、そうしたリスクも見込んで、
棚卸資産は、仕入れと同時に50%の減価と考える方が、より実践的な経営手法だと思います。
しかし、ここにも税務署が仕組んだワナがあります。
本来なら、不良在庫は、それなりの評価減をされるべきものです。
経営者が、自社の実態を知りたいのであれば、
不良在庫の評価減をして、利益を減らすべきだと考えるはずです。
税法は、そのための方法を用意しています。それが、「低価法」です。
低価法とは、期末の時価と比べて在庫の評価が高い場合は、低い方の時価で評価するというやり方です。
しかし、この低価法が中小企業で使われることは、滅多にありません。
なぜなら、時価の評価が困難なため、実際に使われることは皆無だからです。
したがって、不良在庫は評価減できず、
仕入価格のまま、「資産の部」に計上されることになるのです。
● 要因その3 売掛金(貸倒損失・貸倒引当金)
■ 売掛金とは
通常、ビジネスを行う上では、すべての取引が現金取引とは限りません。
1ヵ月の売上をまとめて請求して、翌月末に入金してもらうことは、一般的なこととして行われています。
つまり、「売掛金」とは、売上はたっているが、まだ入金されていない債権のことです。
分かりやすく言うと、会社の取引先に、「売掛金」という形でお金を貸しているのと同じことなのです。
得意先が営業不振に陥ったり、不渡手形を出したりして、債権の回収が困難となった場合には、
「貸倒損失」という経費で、費用計上することが認められています。
貸倒損失で計上できれば、決算書の利益も実態に近づけることができますし、税金面での節税もできます。
しかし、ここにも税務署の仕組んだワナがあります。
実際は、税法上の基準が厳しすぎ、「貸倒損失にしたくてもできない」というのが現状なのです。
そのため、実際は回収の見込みのない売掛金が、資産として計上されており、決算書上は「利益」が水増しされているのです。
税法上の貸倒損失を計上できる条件は、長くなりますのでここでは説明しませんが、
売掛金の中に回収不能な売掛金があれば、本来は、貸借対照表の資産の部から、損益計算書へ振替なければなりません。
しかし、依然として「資産の部」に計上され続けることに、問題があるのです。
● 要因その4 納税・資金繰り
■ 納税資金を意識する
「納税」という言葉を聞くと、多くの経営者の方は「決算期」をイメージすると思います。
決算期に利益が出ていれば、それに対し40~50%の税金を納めれば良いのだから、
「支払いに困る事はない」と考えている起業家もいらっしゃると思います。
しかし、実際には、「税金を支払うために借金をしなければならない」ことが、よく起こります。
これは一言で言うと、「決算書の数字」と「資金繰り」は別モノだということなのですが、
起業間もない経営者であれば、ピンとこないかもしれません。
なぜ、利益が500万円も出ているのに、納税資金の300万円を借入しなければ支払えないのか。
このカラクリを説明すると長くなってしまいますので、ここでは話しませんが、
会社が支払うべき税金の大きなものには、「法人税」と「消費税」があります。
また、税金とは少し色合いが異なりますが、
従業員の給料から天引きしている社会保険料も、納付の対象になります。
ここでは、「税金の支払い方法が、会社の資金繰りを圧迫する」という例を説明してみます。
法人税・消費税は、決算日の2ヶ月後が、納付日になります。
つまり、起業したばかりの会社であれば、最初の一年間は、納税義務がないということです。
2年目以降になると、前年の法人税・消費税の半額を、中間納税しなければなりません。
「中間納税」とは、一年後に支払うべき税金の半分を前払いしておくということです。
つまり、起業2年目には、税金を1.5倍支払う必要があるということです。
もちろん、その期が赤字だとしても、税金は納めなければなりません。
前期同様、儲かっていれば問題はないのかもしれませんが、売上に浮き沈みがあるのがビジネスの世界です。
資金繰りが苦しいところにきて、多額の納税が発生したのでは、泣きっ面に蜂です。
納税できない場合は、税務署に相談して分割払いにしてもらうことも可能です。
しかし、その場はそれでしのげるかもしれませんが、後々この行為が取り返しのつかない事態を引き起こします。
金融機関から、お金が借りられなくなるのです。
保証協会・政策金融公庫といった公的金融機関はもとより、
銀行でも、税金の支払いを滞納している会社に、融資は行いません。
「税金を完納していること」が、融資の条件の一つなのです。
これまで私は、税金の未納のため資金調達することができず、倒産していった会社を何社も見てきました。
それは決して、売上げに伸び悩んでいた会社ではありません。
前期の2~3倍の年商に成長した会社が、
それゆえ、増加した消費税を支払うことができず、志半ばで力尽きていったのです。
ビジネスというものは、「毎月一定の売上が、規則正しく計上される」というものではありません。
必ず、売れ過ぎたり、売れなさ過ぎたりします。
経営者は、「その売上が正常なものか、一過性のものか」の判断に頭を悩ませます。
一度判断を見誤れば、多額の不良在庫をかかえることにもなりますし、
意味のない設備投資に、多額の借金をかかえることにもなります。
経営で一番悩むのは、こうした判断です。
しかし、税務署はそんなことは関係ありません。
出た数字に税金をかけるだけです。
ですから、経営者は、常に納税資金を意識して、経営判断をする必要があります。
納税を考えないで、決算書の利益だけを信じ、外車を買ったり設備投資を行うと、
後で大変な事になってしまいます。
この点は、非常に大切なことですので、よく覚えておいて下さい。
● 要因その5 借入金
金融機関、代表者等からの借入で、資金繰りをおこなっている起業家の方は、非常に多いはずです。
しかし、いまだに、借入金の返済が、経費になるとカン違いしている経営者の方がいらっしゃいます。
ここでハッキリ言っておきますが、経費になるのは「支払利息」だけです。
借入返済の「元金」は、経費にはなりません。
「税引後の最終利益の中から、借入返済を行う」しかないのです。
例えば、借入の年間返済額が、200万円だとします。(減価償却費はないものとします)
これを支払うためには、税引後の利益が、最低でも200万円必要です。
実効税率50%だとすれば、税引前の利益で400万円です。
売上高経常利益率が3~5%の平均レベルの会社だとすれば、売上が8,000万~1億3,000万円なければなりません。
つまり、最低1億円くらいの売上がなければ、借金の返済はできないのです。
会社にとって「借入金」は、あらゆる面で重要な意味を持ちます。
経営者として会社を存続させるには、借入金の知識は必須項目です。
会社を成長させるのも倒産させるのも、「借入金」しだいです。
「会社の実質の借金はいくらなのか?」
「現状で借金はいくらできるのか?」
「無理のない借金はいくらなのか?」
経営者であれば、この程度の質問には即座に答えられなくてはいけません。
運転資金でも設備資金でも、会社の実力以上に無理な借金をすると、
後々返済に苦しみ、破滅への道をたどることになります。
また、借金をする場合には、
「投資したモノが、いつ、いくらの利益を上げてくれるものなのか」を綿密に計算しなくてはなりません。
資金繰りも考慮に入れ、チャンスだと思えば、打って出る必要があります。
それでなくては、企業は成長することもなく、衰退の道をたどることになります。
それほど、「借入金」というものは、会社にとって重要な位置を占めるのです。
「借入金」については、知っておいてもらいたいことが山ほどあります。
例えば、借入限度額の計算方法一つ取っても、10通りの分析法があります。
それに加え、常に循環している事業資金の中で、どうやって適切な資金需要額とそのタイミングをつかめば良いのか。
その方法を知っているのと知らないのとでは、天と地の差があります。
こうした点については、会員用ページで詳しく解説しますので、そちらを参照下さい。
あなたは、見たくない現実を直視できるか!!
―たった一つの知識が会社の明暗を分ける―
これまでのお話でお分かりいただけたと思いますが、
決算書に表示されている「利益」は「本当の意味での利益」ではありません。
決算書に表示されている「利益」というのは、「税務署が税金を取るための数字」に過ぎないのです。
ここに、「税務署用決算書が、いかに実態からかけ離れているか」ということを示す、具体的な例をあげてみたいと思います。
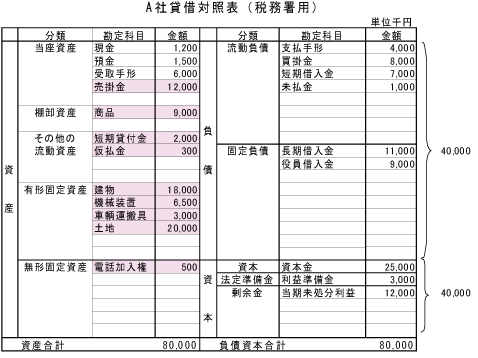
この貸借対照表を見て、どのように思いますか?
自己資本が4,000万円あり、一見良い決算書のように思えます。
これを、実態に即した決算書に訂正してみます。
実態に即した決算書にする場合、ピンク色になっている科目に注意してください。
「売掛金」「商品」「短期貸付金」「仮払金」といった流動資産、「建物」「電話加入権」などの固定資産です。
まず、「売掛金」ですが、税務署用決算書には、すでにお金を受け取ることができないにも関わらず、
まだ売掛金として計上されている金額が含まれていることが多々あります。
これはすでに説明した通り、税法上一度計上した売掛金を、貸し倒れとして処理することが難しいからです。
「商品」も、すでに説明した通りですが、不良在庫が含まれている可能性があります。
次に、短期貸付金・仮払金です。
これらの科目には、社長や役員へお金が流れている可能性があります。
本当に社長への貸付で、すぐに返してもらえるのなら良いのですが、
多くの場合、そのお金は、社長の個人的な支出に使っているため、返してもらえるアテが少ない場合があります。
ここでは、仮払金と短期貸付金で、合計230万円ありますが、全額が返してもらえるアテのないものであれば、実体はゼロです。
ゼロになれば、右側の「資本の部」が、同じ金額の230万円少なくなります。
つまり、230万円の損が増えるということです。
土地・建物といった「固定資産」や、電話加入権などの「無形固定資産」も要注意科目です。
要因その1で説明したように、税法上と実態は全くかけ離れていると言っても差し支えないでしょう。
建物や車などの固定資産は、「今、売ったらいくらで売れるのか」という、実態にあわせた金額を把握する必要があります。
そして、実態の数字は、税務署用決算書の数字よりも低いことがほとんどです。
上記の視点で、実態の金額に修正すると、以下のような表になったとします。

そして、これを元に、実態に即した決算書に訂正してみると、以下のようになります。
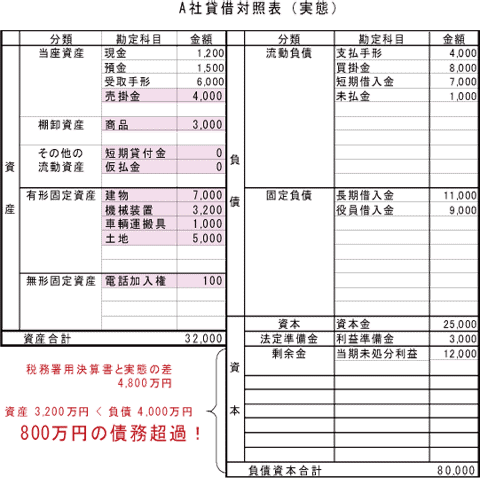
自己資金が4,000万円あり、良い決算書だと思われていたのが、実は「債務超過」だったのです。
このように、実態に訂正してみると、「本当は債務超過だった」ということは、非常によくあることです。
経営者は、見たくない実態を見せ付けられることになりますが、
重要なことは、「その数字から、現状を知り、将来を予測する」ことです。
経営者に大切なのは、「見たくない現実」を直視し、
未来の存続のために、「必要な方策を、一刻も早く打つ」ということです。
あなたは、起業するくらいですから、その専門分野ではプロかもしれません。
しかし、残念ながら、「経営のプロ」ではありません。
経営のプロになるための、必要な知識は、たくさんあります。
その中の一つが、「決算書」です。
「決算書」の数字に関する、たった一つの知識が、あなたの会社のすべてを変える時もあるのです。
「利益は出てるハズなのに、なぜお金は増えないのか?」
起業家であれば、誰もが疑問に感じることだと思います。
税理士に説明を求めると、「入金と出金のタイムラグがあるからだ」とか、「在庫が増えたからだ」とかいう答えが返ってきます。
確かに、その通りなのですが、根本原因はそこにはありません。
理由は簡単なことです。
「儲かっていない」のです。
決算書のルールにカモフラージュされ、儲かってもいないのに税金を払い続け、
「いつか良くなる」と甘い幻想をいだきながら、破滅への道を突き進みます。
会社の現状把握と、数字の意味を理解できていない経営者が、
経営改善目標など掲げることができるはずもありません。
数字を当てはめて作成しただけの改善計画などは、単なる「数字遊び」に過ぎないのです。
経営の世界は、「見たくない現実」をしっかり見た者だけが、生き残ることができるのです。

